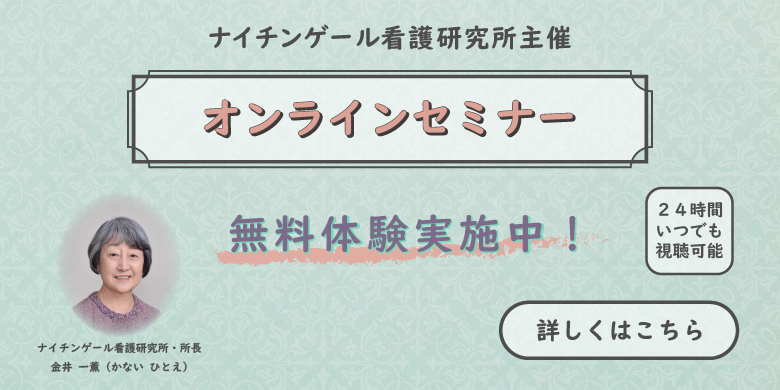膨大な著作から見えるナイチンゲール思想の特徴
ナイチンゲールが遺した150点以上もの著作を紐解きますと、当時のナイチンゲールは最新の知識をもとに、多学問領域にわたる見解を述べていたことがわかります。
結果として、ナイチンゲールには<看護創設者としての業績><病院建築家としての業績><統計学者としての業績>また<衛生改革者としての業績>に加えて<社会福祉家としての業績>など多岐にわたる優れた業績があることがわかってきました。
そうした多領域にわたる業績を踏まえたうえで、ナイチンゲール思想の特徴を著わすとすれば、それはいったいどのようなものになるのでしょう。
本稿では『看護覚え書』をベースに2点に絞って述べてみます。
-1024x769.jpg)
1.『看護覚え書』にみる思想性
当時の英国では、看護と看護師について、はなはだしい偏見と誤解がありました。
看護師と呼ばれる女性たちは、たいてい下層階級の飲んだくれ女で、掃除婦のような仕事に携わっていました。

また上流階層では「失恋か、失意か、厭世か、あるいは他に何の能もないか、どれかひとつあれは、看護師になれる」と考えられていたのです。
それに対してナイチンゲールは、「恋に破れた貴婦人や、生活に追われて救貧院の下働きをしている女性などが、突然思い立ったところで、とてもなしうるような仕事ではない」といって、看護師になる女性たちに向けて、また社会一般の偏見を破るために、『看護覚え書』を通して“本当の看護とはどういうものか”を示そうとしたのです。
誰にでもわかるように、「看護であるものとないもの」を区別する思考過程を示したのが『看護覚え書』です。
『看護覚え書』のタイトルは「Notes on Nursing」ですが、サブタイトルは「What it is and what it is not」となっています。
『看護覚え書』を読めば、何を、どうすることが看護であるかが分かるように解き明かしたのです。
このことから、1860 年当時、ナイチンゲールはすでに看護とは何かという命題をはっきりとつかんでいたことを示します。
彼女は看護に携わる女性たちに看護本来の仕事をするように伝えたかったのです。
この教えは、今日の看護初学者たちにもぴったりと当てはまります。
看護を学び始めるに際しては、「看護であるもの」の姿が明確に示されている本書からの学びは、きわめて有効な手段となるからです。
しかしその思考はすこぶる科学的であり、当時の人々が必ずしも理解できたとは思えません。
つまり看護を実践するにはまず、「病気とは回復過程である」という点の理解から入っていかなければならないと説いているからです。
看護は、体内で発動する回復のシステムに着目して、そのシステムが発動しやすいように、患者を取り巻く暮らしを健康的に整えていくことだと言明しました。
当時の人々には理解が難しかったと思われるこの指摘は、現代の生命科学の知見をもって理解すれば容易に解けます。
その意味でこの思考は、21世紀を見据えるほど斬新なものであり、時代をはるかに先取りしたものだったのです。
結果的に、『看護覚え書』の根底を流れる思想は、きわめて生命科学論的であり、また生命誌論的であると言えます。
しかしながら看護が近代科学分野の仲間入りを果たすためには、このレベルの内容は必要条件であったでしょう。
2.女性の力に託した社会改革
『看護覚え書』の「はじめに」の文章には「女性は誰もが看護師なのである」と書かれています。
現代のジェンダーフリーの思想からみれば、はなはだ偏っているように思われる表現ですが、この中にはある確とした哲学が秘められているのです。
それは、人間の幸福の条件は自己を活かし、健康に生きることにあるというものの見方から出発しています。
ナイチンゲールは<健康>というテーマこそ、すべての人々が追求し実現しなければならない最高の価値であると考えていました。
そして彼女は、看護の機能をその健康の実現というテーマと結びつけ、人が健康に生きていくために暮らしを整えることこそ看護であると説いて、この<暮らしを整える>という発想を最も大事にしたのです。
健康を維持するのも、また病気から快復させるのも、暮らし方ひとつにかかっているからです。
そして『看護覚え書』では、その暮らしを支え、質を高め、管理していくのは、一家の健康を支える女性たちの役割だと説いたのでした。
「すべての女性は看護師である」という指摘は、こうした思想を背景に生まれたものです。
またこの表現からは、社会における看護の機能というものは、決して一部の専門家に帰属するのではなく、すべての人々に向けて開かれたものであることを教えています。
『看護覚え書』は当時、「一家に1冊、看護覚え書を…」と唄われながら広がっていったといいます。
19世紀半ばの英国においては、様々な社会問題が表面化し、心ある人々によって、極貧層の増大に伴う社会の病理現象に立ち向かうべく、社会改善運動が展開され始めた時代です。
格差社会の是正、感染症などの健康問題解決のための公衆衛生改革、住宅問題解消など、それらは主として政治や経済、または福祉などの制度改革を要求していました。

しかしナイチンゲールは、この時代にあって、全く視点を変えて時代の社会病理現象に立ち向かったのです。
それは<貧困><疾病><生活>という分野において、暮らしを担う女性たちに力をつけて、またその力を借りて、その病んだ分野を根底から立て直そうとしたようにみえます。
ここに私はナイチンゲール看護思想の深みを見るのです。
その思想は極めて実践的であり、かつ現実的なものでした。
革命の旗を掲げて闘争するのではなく、まことに静かに、世にあふれる女性たちの力を使って、人間の健康と幸福を実現させようとしたところに、ナイチンゲール看護思想の際立った特徴があるように思います。